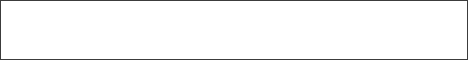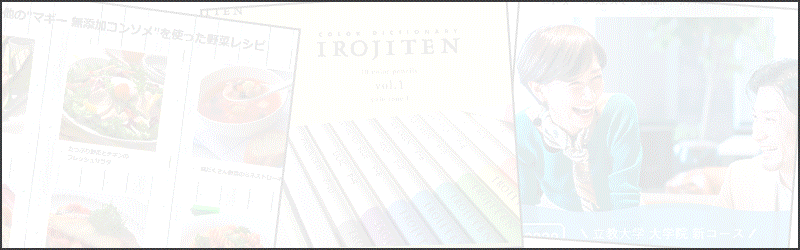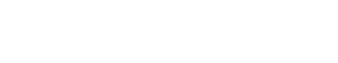今さら聞けない教育DXの基礎知識リンク集 (Ed#8)

前回の「#82 LTIとは?文系でもこれだけで理解できる『教育DX』」では、教育DXを実現するシステム構成を、LTI中心に解説しました。その前に連載した「文系でも理解できる教育DX」シリーズでは、「ラーニングアナリティクス」という角度から、学習分析のために必要な教育DXのシステム構成について6回に渡って解説しています。
これらの記事を順に読んでいただければ LTI 全般について、詳しくご理解いただけるのではと思います。
とはいえ一連の記事を読む時間がない方のために、わからない部分だけすぐにピックアップして確認できるよう、今回は用語や機能レベルでのリンク集を用意しました。
教育DX関連の知識や用語に困ったらご活用いただければ嬉しいです。
【 目次 】
教育 DX のシステム構成について
・教育DXのシステム構成図
※教育 DX のシステム構成をご確認いただける図です
・ツール (Tools)とプラットフォーム (Platform) とは
LTI について
LTI 1.3 について
・LTI 1.1 と LTI 1.3 の違い:セキュリティについて
・Names and Role Provisioning Services (NRPS) とは
・Assignment and Grade Services ( AGS ) とは
教育 DX のデータベースについて
・Learning Locker と OpenLRW の違い
ラーニングアナリティクスについて
教育DXのメリットとデメリット
教育 DX が実現すれば、公務や学習そのもののあり方が変わります。
とはいえそこにはメリットもあれば、もちろんデメリットもあるのでご紹介します。
【教育DXのメリット】
文部科学省の GIGA スクール構想では、以下のようなキャッチコピーが掲げられています。
多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、 子供たち一人一人に公正に個別最適化され、資質 ・ 能力を一層確実に育成できる教育ICT環境の実現へ
<文部科学省 (リーフレット)GIGA スクール構想の実現へ>
一人ひとりに最適化された教材が提供されることで、生徒の習熟度に応じた学習を提供することができますので、授業についていくことができなくなることが原因で落ちこぼれる生徒を減らすことができるでしょう。また、より高度な学習を得たい生徒にとっては、クラスの進捗に左右されずに、最適なスピードで学ぶことができるようになります。
オンライン学習によって、天候や体調などによって移動が難しい時でも学べたり、離れた場所にいる先生から学ぶことも可能です。
また、教員の業務負担軽減という意味でも大きなメリットがあります。
例えば CBT (Computer Based Testing) を活用すれば、公共機関から提供された問題を利用でき、自動採点もしてくれるので、問題作り、プリント、採点などの負担を軽減することができます。
また、ラーニングアナリティクスを活用すれば、生徒の学習状況を把握し、エビデンスに基づいて授業の最適化を図ることが可能です。
【教育DXのデメリット】
デメリットとしては導入のハードルがあげられます。
その一つは教員側の IT リテラシーが求められることです。
これは大きな課題だったのですが、パンデミック以降はオンライン学習が一般的になったことで、教員が教育DXを活用する ITリテラシーの壁はかなり低くなっています。
とはいえいまだ難しいのは、インフラ構築の部分でしょう。
多くの学校にはIT専門部隊が配備されているわけではありませんので、教育 DX を実現するために何から手をつけたらいいかわからないというケースが、ごく一般的なところかという印象です。
確かに、システムの整備やセキュリティの確保などには専門知識が必須です。
しかし、ここでであげたような教育DXの世界標準にのっとってインフラを構築すれば、最新のセキュリティも確保され、今後の拡張性も担保することができるのです。
教育DXをスタートする際には、最初から世界標準を意識して設計されることをおすすめします。
スパイスワークスでは教育DXのインフラ構築、最新の世界標準技術への対応、既存ツールの LTI 対応など、国内有数の実績をもとにアドバイスが可能ですので、こちらからお気軽に相談ください。
【出典・参考文献】
・文部科学省 (リーフレット)GIGA スクール構想の実現へ